|
|
 |
 |
聞き書「秋田の食事」 日本の食生活全集 5
藤田秀司 他編 |
|
|
| ハタハタずし・しょっつる(塩汁)・いぶり大根・各種貝焼(カヤキ)鍋など、自然の要求と人間の要求が一致した発酵食文化の粋・秋田の食事を、農耕・漁労の営みと共に描く。 |
 |
●3,038円(税込)
●A5判、386頁
●86年2月
●農文協 |
 |
| 在庫あり:1〜3営業日でお届けします |
|
|
 |
米と雪の国秋田。がっことはたはたの国秋田。雪と寒さを逆用した発酵・保存食の数々。日本海、八郎潟の豊富な魚、早くから開けた水田の米、奥羽・鳥海山系などの山の幸を、それぞれ巧みな調理加工技術で料理に仕上げる。たんぽ、だまこもち、貝焼きなべ、いぶり大根、どぶろくなど、そのえも言われぬ味覚の数々は、“食通の秋田”の名に恥じぬ、東日本食文化の頂点、味の一大王国を成している。
■「県央男鹿の食」=“しょっつる”にみるわが家の味覚
一、四季の食生活
◎冬…はたはた漁から彼岸まで
家中総出ではたはたとり/食卓を明るくする海草のいろいろ/毎日のように食べるはたはた(日常の食生活)/男鹿ならではのなまはげの行事(晴れ食、行事食)
◎春…にしん漁の出稼ぎから、さなぶりまで
男たちの出稼ぎ/重宝するにしん場からのみやげもの(日常の食生活)/田植えどき、さなぶりの食べもの(晴れ食、行事食)
◎夏…さなぶりからお盆まで
夏の海草と海草料理/あんぷらが食事の主役に(日常の食生活)/鹿島流しとお盆の行事(晴れ食、行事食)
◎秋…お盆すぎからはたはた漁まで
一年中で一番豊富な食べもの(日常の食生活)/行事のたびにもちを搗く(晴れ食、行事食)
二、基本食の加工と料理
◎基本食の成り立ちと料理の手法
ごはん、しとねもの、もち
◎米〈利用のしくみ〉
うめや米、だまこもち、しだもち
◎あんぷら〈利用のしくみ〉
あんぷらもち
◎そば、小麦、大麦、あわ米〈利用のしくみ〉
水あめ
◎大豆〈利用のしくみ〉
豆腐、桶納豆、豆の粉
三、季節素材の利用法
◎海産物〈利用のしくみ〉
はたはたの食べ方−塩ふり焼き、でんがく、味噌味焼き、しょっつる煮、味噌煮、水あぶりなど/いわしの食べ方−いわしとうどの酢味噌あえ、いわしのかまぼこの味噌汁、めがねいわしの煮干しなど/こなごの食べ方/さめの食べ方−刺身、さめかまぼこの味噌汁など/その他の魚の食べ方−あんこうのともあえ/海草の利用−てんぐさ、えごくさ、あらめ、つるも
四、伝承される味覚
◎味噌、しょっつる、醤油の実
◎すしはたはた
由来/つくり方/はたはたのひれや頭だけのすし
◎漬物、食用油、どぶろく
はたはたの塩漬、はたはたのこぬか漬、いわしの塩漬、こぬか漬、こなごの塩辛、しょっつる
五、県央男鹿の食、自然、農・漁業
■「県央八郎潟の食」=子どもも一人前に“ひとり貝焼き”
一、四季の食生活
◎冬…庭洗いから女の節句まで
白魚、ちか、ごり、白目(冬の潟魚)/冬の味・鴨貝焼き(日常の食生活)/冬場に三度ある女の祭り(晴れ食、行事食)
◎春…苗代つくりから田植えまで
ふな、どじょう、なまず、しじみ(春の潟魚)/切干しつくり、山菜とり、味噌の仕込み/朝は食べないなまぐさいもの(日常の食生活)/鎮守の祭りに欠かせないふな、つぶ(晴れ食、行事食)
◎夏…さなぶりからお盆まで
潟舟を引いてするごり漁(夏の潟魚)/野菜を売って買う、まぐろの頭、すじこ(日常の食生活)/お盆に欠かせないところてん(晴れ食、行事食)
◎秋…お盆から庭洗いまで
打瀬船でとる、わかさぎ、白魚(秋の潟魚)/実りの秋をたっぷり味わう(日常の食生活)/節句ごとのごちそうで精をつける(晴れ食、行事食)
二、基本食の加工と料理
◎基本食の成り立ちと料理の手法
◎米〈利用のしくみ〉
つけご、だまこもち、しだもち
三、季節素材の利用法
◎潟魚利用のしくみ
◎ふなの料理
味噌汁、たたきの味噌汁、その他
◎ちかの料理
酢味噌あえ、つくだ煮など
◎ごりの料理
納豆ごりの酢味噌あえ、たたき、つくだ煮
◎しらよと潟がれいの料理
◎えびの料理
塩蒸し、塩辛
四、伝承される味覚
◎味噌、塩辛、醤油
◎飯ずしと漬物
潟がれいの飯ずし
五、県央八郎潟の食、自然、農・漁業
■「県南横手盆地の食」=米どころの米の食べ方ここに極まる
一、四季の食生活
◎冬…えびす講から彼岸まで
一年間の食べものの計画(日常の食生活)/神々の年取りと正月(晴れ食、行事食)
◎春…彼岸から田植えまで
春田打ち=重労働に耐える食(日常の食生活)/一日五回とる田植えの食事(晴れ食、行事食)
◎夏…さなぶりからお盆まで
どじょうなべでお客をもてなす(日常の食生活)/赤ずし、盆ざかな、盆豆腐(晴れ食、行事食)
◎秋…お盆からえびす講まで
なす料理の日々(日常の食生活)/手間とお金をかける祭り膳(晴れ食、行事食)
二、基本食の加工と料理
◎基本食の成り立ちと料理の手法
ごはん、もち、しとねもの
◎米
利用のしくみ、ごはんとしての食べ方(麦飯、赤飯、栗ごはん、こざきがゆ)、もちの食べ方(雑煮もち、小豆もち、豆の粉もち、なべすりもち、ごまもち、じんだもちなど)
◎ひえ、そば、小麦
そば練り、うどん
◎大豆
利用のしくみ、豆腐とじんだ
三、季節素材の利用法
◎野菜〈利用のしくみ〉
にらなます、なすのほど焼き、でんぶごぼう、いものこ汁、いもだんご、いもがら汁、大根葉汁、凍み大根の煮つけ、あじゃら大根、小豆かぼちゃ
◎山菜、その他
柿てんぷら
◎海からの魚、川・田んぼの魚貝
つぶのじんだあえ、つぶの干もの、かにだんご、甲羅味噌
◎果物、おやつ
水あめ
四、伝承される味覚
◎県南の味噌のつくり方
◎がっこ
干しがっこ、なた漬、なすのふかし漬、印ろう漬、おとぎがっこ
◎酒類、飲みもの
あまえこ、果実酒など
五、県南横手盆地の食、自然、農業
■「県北鹿角の食」=味覚を追求して花開いた雑穀食文化
一、四季の食生活
◎冬…庭じめから彼岸まで
米の食いのばしに主婦の工夫でそば粉、豆の粉料理(日常の食生活)/もちを食べる日が月の半分(晴れ食、行事食)
◎春…雪の中の田起こしから早苗ぶりまで
田植えどきの「豆の粉やぎみし」と山菜の煮つけ(日常の食生活)/ごちそうがたっぷりの早苗ぶり(晴れ食、行事食)
◎夏…早苗ぶりからお盆まで
冷たいわき水で食べる季節の野菜(日常の食生活)/赤飯やところてんも供えるお盆(晴れ食、行事食)
◎秋…庭じめでしめくくる収穫の日々
仕事はきついが食べものは豊富(日常の食生活)/出来秋を祝う庭じめのごちそう(晴れ食、行事食)
二、基本食の加工と料理
◎基本食の成り立ちと料理の手法
ごはん、はたきもの、もち
◎米〈利用のしくみ〉
色まま、きゃ干し、だんす、つけ揚げ、しそ揚げ、けいらん、くるみかけ汁もち
◎あわ〈利用のしくみ〉
あわもち
◎そば〈利用のしくみ〉
そば切り、かますもち、そばだんごなど
◎ごしょいも、かぼちゃ〈利用のしくみ〉
◎大豆〈利用のしくみ〉
豆しとぎ、こごり豆、じょやどふなど
◎小豆その他の豆類〈利用のしくみ〉
小豆ばった、きゃの汁
三、季節素材の利用法
◎山菜、きのこ
利用のしくみ、山菜の食べ方(ばっきゃ、あざみ、よもぎ、うど、みず、ぜんまい・ふき・まんたぶなど)、きのこの食べ方(むきたけのなっつ)
◎野菜〈利用のしくみ〉
寒干し大根、干しかぶの煮しめ、青なんばん煮、ささげのにんにくあえなど
◎川や海の魚と貝類〈利用のしくみ〉
さめのお茶わん
◎酒類、果物〈利用のしくみ〉
甘ちこ、あけびの塩漬、あけびのあえもの、あけびのでんがく、むきくるみ
四、伝承される味覚
◎味噌類
玉味噌、青なんばんの三升漬など
◎漬物類
大根なんばん巻き、漬け菜漬、大豆入り大根のなた切りとかぶ漬、梅干しっこなど
五、県北鹿角の食、自然、農業
■「県北米代川流域の食」=雪の夜はたんぽ鍋に舌つづみ
一、四季の食生活
◎冬…行事とごちそうの日々
自慢の漬物、酒っこに話の花が咲く(日常の食生活)/神さまの年取りと人間の年取り(晴れ食、行事食)
◎春…農作業はじめから田植えまで
にしん、納豆、酒っこが働く力に(日常の食生活)/ひな祭り、春祭りの喜びと、さなぶりのごちそう(晴れ食、行事食)
◎夏…田の草取りからお盆まで
夏野菜がたっぷり(日常の食生活)/忙しくても心なごむお盆(晴れ食、行事食)
◎秋…出来秋を祝う刈上げの節句
涼しくなると納豆をつくる(日常の食生活)/地鶏をつぶして味わう新米のたんぽ(晴れ食、行事食)
二、基本食の加工と料理
◎基本食の成り立ちと料理の手法
ごはん、しとねもの、もち
◎米〈利用のしくみ〉
もち米(強飯、なべもち、ぶどう混ぜずし)、うるち米(味噌つけたんぼ、たんぼ貝焼きなど)、はたきだんご(しとね汁もち、串もち、ごまだんご、だんし、かまぶく、凍しもち、寒ざらし粉)、もち(歯固めのもち、ふくれもち、あられっこ)
◎大豆〈利用のしくみ〉
こが納豆、雪納豆、納豆汁など
◎小麦、大麦、あわ、ひえ、そば
きゃもち、そばもち、うちわもち
三、季節素材の利用法
◎野菜、山菜、きのこ〈利用のしくみ〉
とんぶりの食べ方、煮しめ、大根しみさ
◎果物、木の実、おやつ
あけび味噌焼き・袋詰め、マルメロ砂糖漬
◎海の魚貝、海草
てん、めまき、かすべのからぎゃ煮
◎川、水路の魚
くらこなます
四、伝承される味覚
◎味噌
玉味噌、たまり、すまし
◎漬物
なた漬、生こぬか漬、しょっつる漬のなす焼き、にしんのこぬか漬・切りこみ
◎すし
すしはたはた、けいとままなど
◎食用油、砂糖、食酢
◎酒類
ぶんど酒
五、県北米代川流域の食、自然、農業
■「奥羽山系(田沢湖)の食」=どぶろくを飲みつつ味わう、うさぎ鍋
一、四季の食生活
◎冬…神さまの年取りから彼岸まで
ねりかゆ、のせままで節米(日常の食生活)/神々の年取りと正月のごちそう(晴れ食、行事食)
◎春…彼岸からさなぶりまで
春の香りがいっぱい(日常の食生活)/行事につきもののどぶろく(晴れ食、行事食)
◎夏…さなぶりからお盆まで
実だくさんの味噌汁とさわし飯(日常の食生活)/心をこめてつくるお盆のお供え(晴れ食、行事食)
◎秋…二百十日からお稲荷さんの祭りまで
かに味噌、かにたたきは秋の味覚(日常の食生活)/神々に豊作を感謝して(晴れ食、行事食)
二、基本食の加工と料理
◎基本食の成り立ちと料理の手法
ごはん、しとねもの、もち
◎米〈米利用のしくみ〉
三ばいみそ、しとね口取りなど
◎大豆、その他の豆
利用のしくみ、豆腐の作り方(凍り豆腐、いもかけ豆腐、八杯豆腐)、納豆の作り方(火棚納豆、引割り納豆)、納豆の食べ方
三、季節素材の利用法
◎山菜〈利用のしくみ〉
こごみ、ぜんまい、わらび、ねばなもち、たけのこ、みず、いとさく、ほなこ、しゅでこ、たらの芽、ふき、しどけ、ゆり根
◎きのこ
きのこの漬けこみと塩出し
◎野菜
利用のしくみ、大根と二度いも
◎果物、おやつ
炒り豆
四、伝承される味覚
◎どぶろく
◎漬物
たくあん漬、生漬大根、なす漬・きゅうり漬
◎魚のすし漬
はたはたずし、かどのこぬか漬
◎味噌類
味噌、しょゆの実
五、奥羽山系(田沢湖)の食、自然、農業
■鳥海山麓由利の食
山と川の恵み(ぞうすいだんご、松皮もち、たらのしょっつる、あんこうのともあえ、はたはたの干しか、てん、つき豆腐、焼き豆腐、豆腐粕、うさぎたたき)
■人の一生と食べもの
一、凶作と飢餓−救荒食
ねばなもち(わらびの根もち)/くず粉/しだみもち、とちもち
二、薬効のある食べもの
三、お産と食べもの
■秋田の食とその背景
一、日本の中の秋田−秋田の食の特徴
自給型食生活の原点、明確な地域性、むらの暮らしと行事食・晴れ食の伝承、長い冬に備えて、特異な調味料と大豆食品
二、秋田県の地域区分
三、食を支える自然と農・漁業
◎県央男鹿の食、自然、農・漁業
男鹿の歴史と自然/男鹿の漁業、農業/北浦−はたはた漁の中心地
◎県央八郎潟の食、自然、農・漁業
八郎潟の歴史と自然/魚の宝庫−水一升に魚四合/八郎潟の農業−腰までぬかる湿田
◎県南横手盆地の食、自然、農業
雄物川、玉川流域の沃野/屋敷畑、岡畑、川原畑、山畑/山や川とのかかわり/海とのかかわり
◎県北鹿角の食、自然、農業
鹿角の自然と産業/鹿角の伝承料理と民俗行事/鹿角の農業−冷涼な気温/黒沢地域の暮らし−生活の糧となった山と川
◎県北米代川の食、自然、農業
大館盆地の自然と農業/山や川、海とのかかわり/働き手の牛や馬
◎奥羽山系(田沢湖)の食、自然、農業
山に囲まれた盆地/山里の農業/山や川とのかかわり/海とのかかわり
■秋田の食−資料
◎県央男鹿の魚と海草の利用
◎県南横手盆地の四季の食事例(基本食とその食べ方、年間の食生活暦)
◎県北鹿角の山菜、きのこ、その他の利用
◎県北米代川流域(大館、板沢)での基本食とその食べ方
◎奥羽山系(田沢湖)での山菜、川魚、海産物などの利用
■索引
■付録
■調査・取材協力者一覧
|
 |
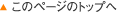 |
|
|
|